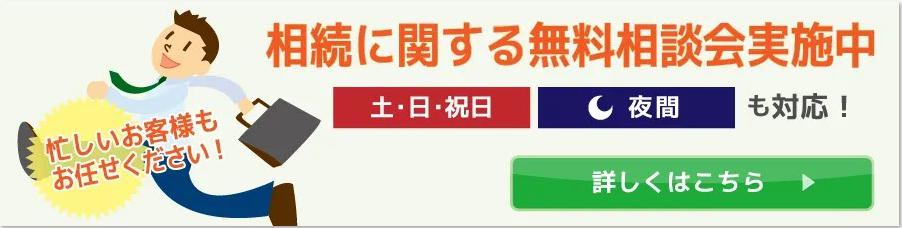相続税の配偶者控除とは?注意点も併せて解説
相続税には、配偶者が受け取る財産に対して大幅に税負担を軽減する「配偶者控除」という特例があります。
しかし、適用条件や二次相続の影響を考慮しないと、後々の相続で思わぬ負担が生じることがあります。
今回は、配偶者控除の仕組みと注意点を詳しく解説します。
配偶者控除の概要
配偶者控除は、被相続人(亡くなった人)の配偶者が相続する財産に対して適用される特例で、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」の多い方の金額までが非課税となります。
そのため、配偶者が多くの財産を相続する場合でも、一定額までは税負担が発生しません。
配偶者控除の適用条件
配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 被相続人の法律上の配偶者であること(内縁関係の場合は対象外)
2. 相続税申告を行うこと(無税でも申告が必要)
3. 申告期限内に遺産分割が完了していること(相続開始の翌日から10か月以内)
二次相続の負担に注意
配偶者控除を活用すると、一次相続(夫婦のどちらかが亡くなったとき)の相続税負担を大幅に減らせます。
しかし、その配偶者が亡くなった際(二次相続)には、この特例は適用されず、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
たとえば、一次相続で配偶者がすべての財産を相続し、相続税はゼロであった場合で、次に配偶者が亡くなった時(二次相続時)に子どもがすべてを相続した場合、配偶者控除が適用されず、高額な相続税が発生する可能性があります。
このように、一次相続で配偶者控除を活用しすぎると、二次相続で税負担が増大する点に注意が必要です。
節税対策としての財産分割
二次相続の税負担を軽減するためには、一次相続の段階で配偶者と子どもに分割して相続することが有効になる場合があります。
一部を子どもが相続することで、配偶者が亡くなった際の相続財産を減らし、一次相続と二次相続の合計の税負担を軽減することが期待できます。
まとめ
配偶者控除は、一次相続での相続税負担を大幅に減らせる制度です。
しかし、二次相続では適用されず、結果として子どもが高額な相続税を支払うリスクがあります。
そのため、配偶者だけでなく子どもにも一部財産を相続させるなど、長期的な視点で相続対策を行うことが重要です。
相続税対策に不安がある場合は、税理士に相談しながら計画を立てることをおすすめします。